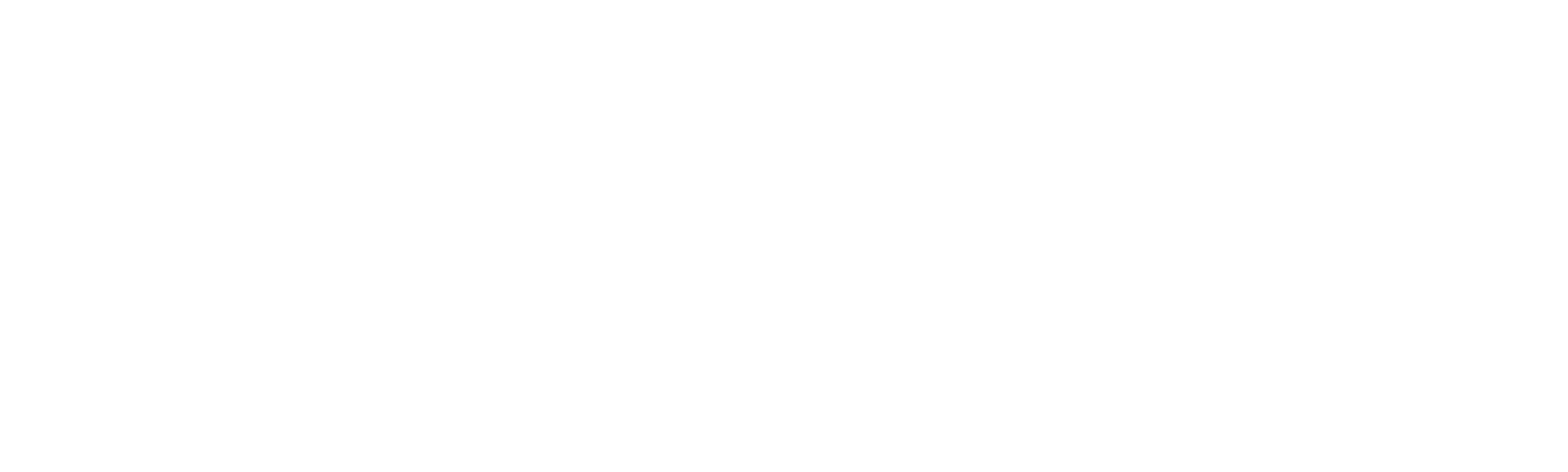ご覧いただきありがとうございます。
初めまして。
橘家の「レモン」と「みかん」です。
私たちは、【豊かな暮らし】を目指して、三重県いなべ市に引っ越してきました。
私たちが描く【豊かな暮らし】の中には食の自前、すなわち食の自給自足があります。
自給自足でも「安全で安心できる食」を自給できるように日々全力で取り組んでいます。
そこで「私たちが安全で安心できる食」の基準は、極力自然のまま、余計なものを入れず、人が手を加え過ぎず、その土地や環境に順応して作られたり、育ったものと考えています。
食の大切さを知ったキッカケ
私たちは、2013年の東日本大震災を東京で経験しました。
都心では交通機関がとまり帰宅難民が溢れ、コンビニやスーパーマーケットでは、食料の争奪戦、買い占めとなっていました。
物流システムに影響して食料が入ってきませんでした。
数日まともに食事をすることができず危機感を感じました。
また被災地の福島へ水と食料をもって支援へ行ったとき、食べていくことができなければ『生きていくことが出来ない…』そう強く感じました。
当り前のことなのですが現実をはっきりと目の当たりしました。
そこから「食」に対して意識し始めます。
更に2020年頃から流行したコロナウイルス。国を信じ、メディアを信じ、ワクチンを2回接種するもコロナに発症し高熱がでて1ヶ月近くの味覚障害に。
数年後、WHO(世界保健機関)がワクチンを推奨しない(=オススメしない)と明言。その時に、薬やワクチンに頼るのではなく1『免疫』を高めた方がよっぽど理にかなっていると思うようになりました。
厚生労働省:WHOの新型コロナワクチンの利用に関する指針(概要)(2023年3月30日 公表)
講談社:2023.04.12 突然のWHO「ワクチン推奨しない」発表に「打つんじゃなかった」と思った人へ…手を洗う救急医Takaさんに本当の意味を聞いてみた
食品にも違いがあると学んだ
私たちは過去の経験から、まずは自分の体にある「免疫」を強くしたいと思うようになりました。
どうやったら
『免疫』を強く出来るのか…?
↓
人間の体は食べたもので作られる。
↓
免疫も食べたもので作られる。
↓
「食事」を見直してみよう
連想ゲームのように、最終的に「食事を見直す」に落ち着きました。
しかし「食事を見直す」と言っても、何から始めたらいいのかわかりません。
今までは共働きの子育て世代にとってはありがたい「手軽・美味い・安い・そして日持ちする」という基準で商品を選んでいました。
なので、まずは近所のスーパーで買い物をする時に【食品の裏にあるラベル】を見てみることにしました。
最初に気になったのが、ラベル表記に載っている「食品添加物」。聞いたことはあるけど、そもそも食品添加物2ってなんだろう?と疑問に思い、少しずつ調べていきました。
調べていくと、天然素材を加工しているものもありますが、実は食料品のように見せている工業製品が多いではありませんか。
化学合成添加物には注意が必要! 食の安全講演会開く 京都府保険医協会
【一部抜染】
合成添加物では、特に人体に影響が考えられる添加物として、発色剤の亜硫酸ナトリウム、カラメル色素、合成甘味料3品目(アスパルテーム・アセスルファムK・スクラロース)、パン生地改良剤の臭素酸カリウム、合成着色料のタール色素、防カビ剤のOPPとTBZ、殺菌料の次亜塩素酸ナトリウム、酸化防止剤の亜硫酸塩、合成保存料の安息香酸ナトリウム、合成甘味料のサッカリンナトリウムが挙げられた。これらは発がん性、催奇形性などの疑いがあり、また急性毒性が強く、臓器に障害をもたらす可能性があるなど、それぞれの危険性を指摘した。
例えば、加工肉によく使われている「亜硝酸ナトリウム」は、下記のように説明されているのです。
亜硝酸ナトリウムとは何? weblio辞典
工業的な製法では、アンモニアを酸化して得た一酸化窒素と二酸化窒素を炭酸ナトリウムないし水酸化ナトリウムに吸収させて合成する。
説明で、『工業的な製法』って記載されていますやん…。
もしかしたら、もっと他にもあるのでは…?
こんな風に本やインターネットから少しずつ情報を集めていきました。
特にわかりすかったのが下記の情報です。
①添加物で実際にニュースになった事例と共に説明を記載している「郡司和夫3さん」が書いた本

単行本 – 2008/10/1 郡司 和夫 (著)
②実際に実験して検証している「阿部司4さん」のYouTube
生産・製造工程や、その材料や餌まで見ることが大切だと知った
このような経緯から、購入する食品も裏にあるラベルだけでは安心できず、どう作られ・育てられているのかも気になりだします。
例えば、過去にコンビニ弁当を食肉用の豚の餌にしたところ、奇形や死産が多くなったというニュースがありました。
第24号:食の安全 -コンビニ弁当から思うこと(前編)- 日本獣医生命科学大学
【一部抜染】
西日本新聞社発行のブックレット『食卓の向こう側』によれば、「福岡県内の養豚農家で、あるコンビニの弁当やおにぎりを母豚に毎日3キロずつ与えたところ、奇形や死産が相次いでいたことが分った。」そうです。豚の体の構造は比較的人間に近く、非臨床試験などにも用いられる動物です。さすがに人は1日に3キロもコンビニ弁当を食べないにしても、誰もが一度はお世話になったことのあるコンビニ弁当。これはちょっと注意が必要だと感じました。
そうなると、食物連鎖5の中にいる人間にとっても無関係ではいられません。
食用のお肉。牛や豚、鶏などが食べている餌は、本当に安全なものなのか?
農薬や化学肥料を使っている作物は本当に大丈夫なのか?
「栽培中無農薬」ってそれ以外の期間に散布した農薬や除草剤とかって土壌に吸収されないの?
あげたらキリがないくらい、次々と疑問が浮かんできます。いつしか、生産者の作る過程が見れないならば、自分で作れるものは極力、作ってみたい!と考え始めるようになっていきました。
そう考え始めた頃に、無農薬栽培をしている農家さんのお手伝いをさせていただく機会がありました。そこで、本当に衝撃を受けたのが、野菜の種です。
外国産の為、種を守るために、種の周りに農薬コーティングがついているものを利用していたのです。
「それぐらいええやん」
「細かすぎるやろ!」って
お言葉も聞こえてきそうですが…
私は、「無農薬」って言うなら、そこまでこだわれよ!消費者をバカにしているのか?っと感じてしまったのです。感情論ですが、それなら、「減農薬でやっています。」や地域の耕作放棄地を守る為、日本の農業を守るために「慣行栽培やってます!」って言うほうが潔くてカッコいいと思っています。
ちなみに私は、「○○栽培はダメです。」と言いたい訳ではありません。私はどんな栽培方法でも、購入者自身が納得していれば問題ないと考えています。
私が伝えたいのは、添加物にしても、農薬にしても、「無知な消費者(=買い手)を騙す」ようなことはしてない。そして買う側も「体が作られる食べ物」に対して、興味を持ち、知識を身に着けることが大切だということ。その上で、購入する選択をした方がその人自身の為になるということです。
私はこれまで「手軽・美味い・安い・そして日持ちする」を意識して買い物をしてきました。なんの疑いも持たずに作るのが面倒くさいという理由だけで、自分の赤ちゃんの離乳食すらレトルトに。ファーストフード通いはあたり前。惣菜なんて毎週のように大切な家族に食べさせていました。そんな頃は、肌荒れもすごく、長男は不明熱で入院したり、夫も毎年、体調不良で寝込むことに…。
こんなことが続いていたので、物は試しに、食材を厳選し自炊中心の食事に変えたところ、本当にパタリとなくなっていきました。
このことから以前のままの食生活を続けていたら、より大きな病気になるかもしれない。ましてや健康を害するだけはなく、仕事を休んで看病、病院に薬と更にお金がかかり、生活はより苦しくなるかもしれない…。
まさに金儲けの餌食になっていたのではないかと頭がよぎります。なんとも言えない、恥ずかしく、悔しく、そして情けない感情でいっぱいでした。
この体験から、私たちのような思いをしてほしくない。誰かが手遅れになる前に、誰かの気づきになったら嬉しいと思い情報発信を始めたのも1つの理由です。
過去は変えられません。これを機に次の買い物から『どこで、どんな人が、どのように作っているのか』を意識して食材を買ってみませんか?
私たちが目指す、食の自給自足
私たちが【豊かな暮らし】を目指して、田舎移住を考え始めたのが数年前。実際に行動するべく、東北や北陸など様々な田舎を見て回りました。
その中でも移住体験で、直接お会いし感銘を受けたのが、福井県大野市の自然栽培米農家「四郎兵衛」松田雅之さんです。
無農薬・無肥料栽培で目指す福井の自然栽培米農家「四郎兵衛」松田雅之さん/福井県大野市 NIHONMONO
【一部抜染】
「奇跡のりんご6」を見て、自然栽培に強く興味を抱く
さらに情報を集めるうちに、自然栽培のカリスマとして知られる木村秋則さんの、映画にもなった著書「奇跡のりんご」にたどり着いた。ありのままの環境で育てる農法に強く興味を持ち、週末や有給を使って各地の自然栽培のセミナーや講習会に参加するようになる。「多くの講習会に出て一番驚いたのは、無農薬・無肥料の米を炊きたてのまま瓶に入れて蓋をしておくと発酵して良い香りがしてくること。有機栽培の米は腐敗してドロドロになっていくだけでした」。探していたのはこの農法だ、残った人生はこれにかけようと松田さんは自分の米づくりの方針を決めた。
私たちは、松田さんから、この記事に書かれている瓶を見せていただきました。(=異なる栽培方法で作られた米を、同じ水・時間で炊いたものを各瓶に詰め、数年立って検証したもの)
その瓶を1つ1つ手に取り、目にし、香りをかぎました。1つはカビていたり、1つは腐敗していたり、1つはドロドロだったり…
しかし、無農薬・無肥料の米だけは、今もなお甘く発酵し続けているいい匂いだったのです。同じ米でも、栽培方法が違うだけで、こんなに違うのか…とまたもや衝撃を受けたのです。
そして、松田さんのお話を聴いていくうちに心が大きく揺さぶられたのを今でも鮮明に覚えています。
松田さんは、ご両親に農薬を振ったと嘘をつき、地域では変わり者扱いをされたという苦労話。周りから迷惑がられ、反対され続けても、信念を曲げずに今でも挑戦し続けていること。挑戦している最中に、確かに少しずつ作物が良くなっている手応え。安全で安心できる米を作りたいという想い。
気づいたら、聴いているうちに、目に涙が浮かび、こぼさないよう必死に耐えました。
そこで教えてもらったのは、極力、余計なものをいれず、人が手を加え過ぎず
①“山林は山林、田は田、畑は畑という使い方をすること”
②“除草剤も使わないから、草刈りに大半の時間を奪われること”
③“自然な土壌になるのには、とても時間がかかること”
このような実体験から、自分たちで食べるものぐらい、納得するもの作ってを食べよう。作り方は、極力自然のまま、余計なものを入れず、人が手を加え過ぎず、その土地や環境に順応していく方法。
私たちはそう、志、三重県いなべ市で
【百姓】を目指し活動をしています。
(※百姓=農家ではなく、生きていくために必要な様々な仕事に携わる人)
最後に伝えたいこと
私たちは、お互いに住宅街のサラリーマン家庭で育ち、農家の跡取りでも、作り方を学んだこともありません。もちろん、農地や農機具・工具も持っていません。
今は、やっと農地を貸していただくことができ、米作りも野菜作りにも挑戦できる土俵に立つことができました。そして作物を荒らす、獣害対策として狩猟にも挑戦しています。こちらに関しても知識や経験はありません。狩猟と言っても幅広く、私たちの信念として、むやみやたらに捕まることはしていません。ただ獣害対策の一環で捕まえたからには、ありがたく命を頂戴し、無駄にすることなく食べることを徹底しています。
正直、大変な日々かもしれません。毎日、試行錯誤しながら突き進んでいる状況です。けれど、とても楽しく、充実しています。今後は、私たちの奮闘を掲載し、このサイトを読んでくださる人やその家族、身近な大な人を守れるようなる為のヒントが提供できれば嬉しいと考えています。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
ぜひ、気になる記事があればご覧ください。
参考
- 免疫とは、細菌やウイルスなどの異物が体内に侵入するのを防いだり、排除したりして、体を守る力のこと。 ↩︎
- 食品添加物とは、加工食品をつくるときに、形や味を整えたり、色をつけたり、くさりにくくしたりすために加えられるもののこと。 ↩︎
- 日本人の“命”を縮める「食」単行本 – 2008/10/1 郡司 和夫 (著) ↩︎
- 阿部司 食品の裏側 ↩︎
- 食物連鎖とは、生き物たちが「食べる・食べられる」の関係でつながっていること ↩︎
- 奇跡のリンゴ―「絶対不可能」を覆した農家 木村秋則の記録 (幻冬舎文庫) 文庫 – 2011/4/12
石川 拓治 (著) ↩︎
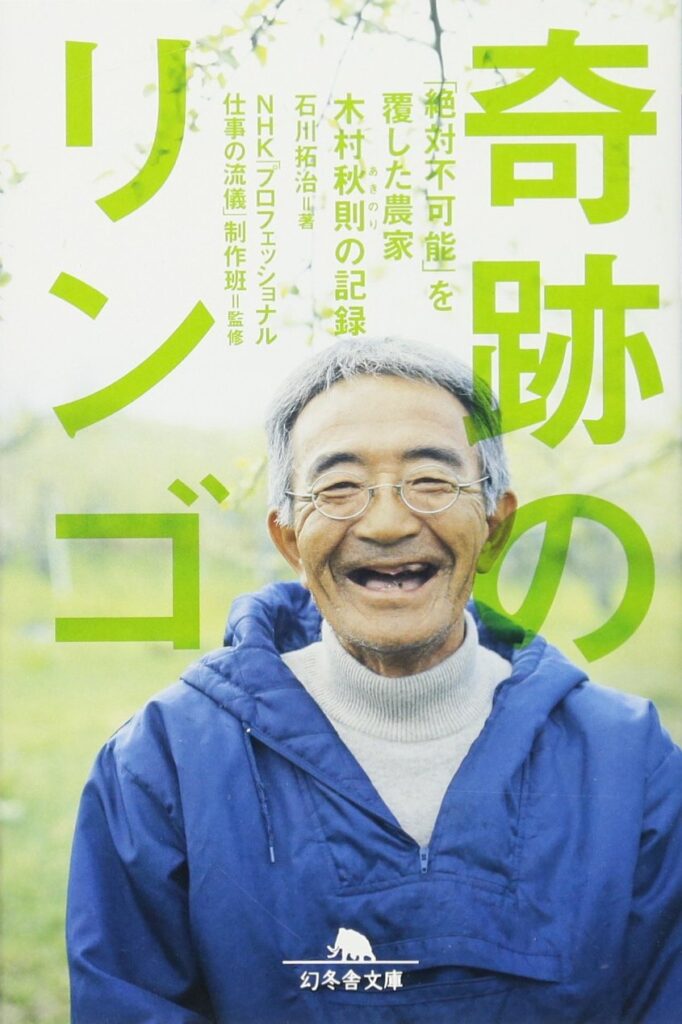
木村秋則の記録 (幻冬舎文庫) 文庫 – 2011/4/12
石川 拓治 (著)